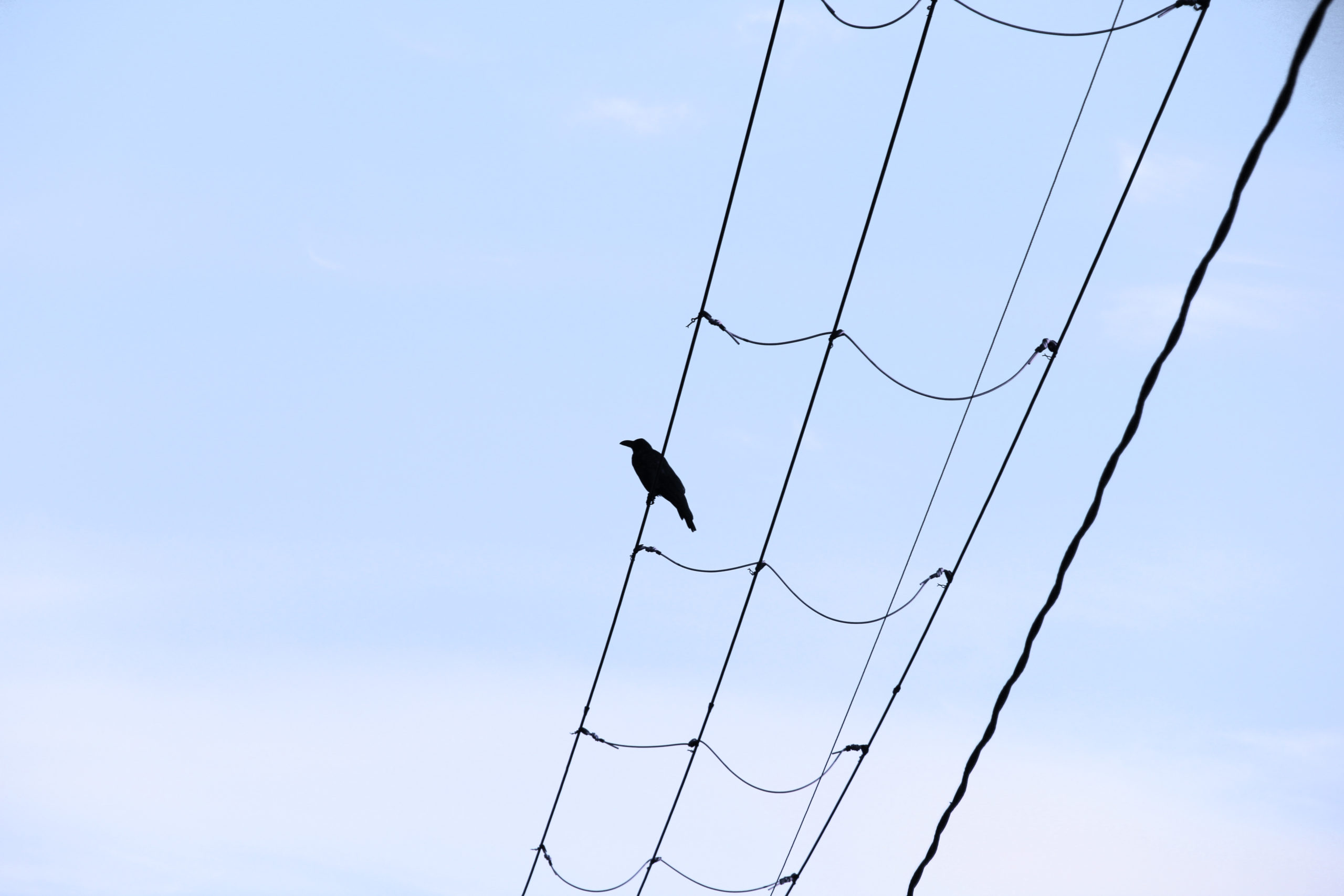明け方の五時まで饗宴は続いた。終わればホステスたちはさっさと帰って行った。ビン子ママが奥のテーブルで伝票の束と電卓を片手に今日の売り上げの計算している。咲知はテーブルの下げものを手伝ってくれた。洗いものを全て片付け、ビールとワインの空き瓶をケースに入れ、ゴミを外の収集所に出して終わる。一時間後にビン子ママが一階のシャッターを下ろして無事に閉店した。慣れない仕事で全身が軋んでいたが咲知と一緒の帰路は仕事をやり遂げた充実感もあって疲労感さえ心地よく感じた。しかしオカマたちみんなが咲知との同棲を知っているようで仕事に支障はないのか不安で咲知に聞いてみた。
「咲知さん、お店のみんなは僕たちが一緒に暮らしているのを知ってるの?」
「ええ、知ってるわ。みんな上手く行くように応援してくれてるわ。それに隠しててもいずればれるでしょ?秘密がばれることに怯えて暮らすのはもう嫌なの。そう思わない?」
「はい。堂々と生きましょう」元いた世界の人間たちとこの世界の人間たちの全く違うことが可笑しかった。退職して良かったとこの時思った。車も人影もなく夜のネオン煌めく喧噪の街が今は静寂に包まれていた。空はすっかり白んで御苑辺りから数羽の鴉の啼き声が聞こえた。
二日前に麹町の弁護士から連絡があり今日は弁護士立ち会いのもと由起と慰謝料、財産分与、養育費に関する離婚協議書の署名押印をしなければならなかった。約束の時間より早めに着いて事務所の相談室に通されドアを開けると一瞬目が眩んだ。由起だけでなく由起の両親も同席していた。一斉に三人の鋭い視線が小河原に突き刺さった。弁護士が協議書を小河原の前に置いた。小河原は署名し押印して弁護士に手渡すと由起も同じようにして手続きが終わった。
「これで契約が成立いたしましたので小河原さんは来月から滞納がないように養育費と慰謝料の支払いをお願いします。滞納した場合、あなたの給料の差し押さえや制裁金が課せられることがありますから気を付けてください」
弁護士の声だけが虚しく聞こえ、由起と両親は小河原の顔を恨みがましく睥睨している。ついに由起の父親が自分を抑え切れず口を開いた。
「一体このざまは何だ?お前は父親の自覚があるのか?自分の妻と息子に対して責任と言うものはないのか?それにお前は何でも男と暮らしているそうじゃないか。そんな変態趣味があるのなら何でうちの娘と結婚したんだ?えっ、答えてみろ!」
由起の父は甲高い声で捲し立てた。
小河原は「すみません」とだけ言い、何も言い訳はしなかった。由起から疎まれていようと和也に蔑まれていようとそれは小河原の家族に対する努力不足が原因で、全ての罪を背負い込んで生きて行こうと思った。由起の父は「すみません」としか言わない小河原に余計苛立ち追い討ちをかけた。
「後ろめたいから何も言えないんだろう。いい歳してオカマなんかと付き合いやがって!男として父親として恥ずかしくないのか?……大体、お前に初めて会った時からどうも気に入らなかったんだ。何考えてるか分からないしいつもおどおどしてるし。男はもっと堂々として逞しくなきゃ駄目なんだ。お前みたいに軟弱な男が家庭を守れるか!」
「小河原さん」その隣に座っていた由起の母親が話し始めた。
「由起は子供の頃から素直で優しい子だったんです。それなのにあなたは浮気して、オカマと一緒に暮らして、由起を悲しませるなんて、何でそんな酷いことができるんですか?………私の夫は今まで女遊びも浮気もしたことない立派な人です。大企業の部長として六十まで懸命に働き全うしました。亭主の鏡です。あなたもこの夫をお手本にして由起と和也を幸せにしてくれるものだと思っていました。それが何ですか?この有様は?」
由起の母はハンカチで目頭を押さえ鼻を啜リ始めた。最後に由起が小河原を詰った。
「お父さんみたいな立派な人間になってって何度も私はあなたにお願いしたわよね。でもあなたはなれなかった。なれる素質もなかった。駄目な人間はずっとダメ人間ね。それにあなた、会社辞めたんでしょ?会社に電話したらもう退職したって言うじゃない?どうするのよ?慰謝料と養育費」ねちねちと厭味っぽく言われた。
「大丈夫です。何とかきちんと払います」
「駄目な人間は何をやっても駄目ね。辞めたんじゃなくて馘になったんでしょ?」
小河原は返す言葉もなかった。胃液が逆流して来た。
「どうやら図星みたいね。本当に情けない。あー、あなたとの結婚生活は本当に無意味だったわ。凄く後悔してる。このままじゃ気が済まないわ。あなただけオカマと幸せに暮らすなんて許せない。必ずあなたたちの仲を壊してやるから覚悟しなさい!」
由起はそう言い残すと両親とともにそそくさと相談室から出て行った。
二週間も経つと小河原の体はバーテンダーの仕事に慣れて筋肉痛も起こらなくなった。大凡の仕事は覚えたつもりだがカクテルの作り方はさすがに二週間の仕事の合間では身に付くものではなかった。不安そうな表情の小河原を見て「それならバーテンダーの学校に行ってみたらどうか」と依田が助言してくれた。
咲知のパソコンで小河原は学校を捜した。一ヶ月間のカリキュラムで終わる渋谷のバーテンダースクールを見つけた。午後三時から六時までの三時間。毎月開講して入学しやすく卒業しやすい学校だった。授業料もそれ程高くなく何とか残りのへそくりで支払うことができた。一クラスに二十人ぐらいの受講者がいた。若い生徒ばかりで小河原程、歳を取った生徒はいなかった。最初の二日間、講義が退屈で続けられるのか不安だったが三日目の実習から小河原は久しぶりに学ぶことの楽しさを味わうことができた。
授業が終わると少し早目だが六時半過ぎにはクラブマカオに出勤できた。コンビニでサンドイッチと牛乳を買ってまだ誰もいない店の中で小腹を満たしそれから掃除を始めた。フロアの隅々まで掃除機を掛け、テーブルは丁寧に布巾で拭き取り、トイレも洗剤を使って水垢、黄ばみをブラシで落した。グラスは一点の曇りもないように磨き上げた。今夜もオカマたちの饗宴が始まる。
オカマたちの正味八時間の労働が終わり、明け方、閉店間際にビン子ママが小河原の歓迎会と依田の送別会を開こうと言い出した。明日は休業日。オカマたちは狂喜乱舞した。 店近くの正午まで営業している焼肉屋で会は開かれた。オカマ八人に小河原と依田、合計十人が三つのテーブルに付いた。まずは生ビールをピッチャーで二つ注文してそれぞれ大ジョッキに注ぎ合っている。乾杯の音頭はビン子ママだった。
「ヨーダさん、長い間ありがとう、そしてお疲れさまでした。本当にヨーダさんにはお世話になりました。お店を辞めても元気でいてね。それからオガちゃん、クラブマカオにようこそ。これから宜しくね。それじゃあ、かんぱーい!」
エネルギッシュな乾杯の雄叫びが店内に響く。小河原は一瞬耳鳴りがした。店員を即座に呼んで三田マンジョビッチが注文し始めた。肉はカルビ、ロース、ハラミ、タン、ミノ、ホルモン、丸腸、コリコリ、レバー、ユッケ、豚トロ、それぞれ大皿で二皿ずつ注文した。メニューの上から下まで順に注文しているようだった。
「それからあなたも~生で~」マンジョビッチが若い店員を指差してからかっている。ウェイターが怯えながら次から次へと大皿を運んで来るが、テーブルの上に乗り切らず隣のテーブルにまで乗せている。一斉にオカマたちがカルビから網に乗せ始めた。焼肉にもクラブマカオのオカマなりのルールがあるようだ。それを仕切っている焼肉奉行はマンジョビッチだった。
「よし!」マンジョビッチが肉の焼け具合を箸で確認して号令した。
一斉にオカマたちは肉を食し始めた。この人たちは肉食だ──。小河原は圧倒された。上品に女性らしさとは程遠く獣のように肉を貪っている。「生きる」と言うことは「食べる」ことだと実感した。只管貪り食い、泥のように眠る。食欲と睡眠欲、それが人間の二大本能だと言われるが正に彼らは人間らしく生きている。しかし彼らのもう一つの本能、性欲が人間らしいのかどうかは分からなかった。
ふと小河原は五年前に亡くなった母を思い出した。母の死に際は自分で栄養を摂れず胃ろうで延命処置を施した。食物を手に取る力、咀嚼する力、嚥下する力のない人間には自ずと死が間近に迫って来る。その自然に逆らって医者は人間を生かそうとする。「生きている」とは到底言い難かった。担当医に小河原は泣きながら懇願した。「頼むからもう胃ろうは止めて欲しい」と。それでも医者から「人道的にそれは許されない」と小河原の申し出は拒否された。母は肺炎を起こし全身が浮腫んで苦痛の果て死を迎えた。あの無駄な苦しみは母の人生に必要だったのだろうか──。最近では家族や本人が胃ろうを拒否できるようになったと聞く。もう少し早く拒否権が認められていれば母は楽に死ねたかもしれない。
上座に依田が座り隣の小河原が依田にビールを注ぎながら礼を言った。
「どうも色々お世話になりました。勉強になりました」
「これからですよ。頑張ってください。バーテンダーは乱れた気持ちでカクテルを作ると味も乱れてしまうんですよ。だから日頃の規則正しい生活が大事です」
「規則正しい生活ですか?難しいですね。でもそう心がけます」
「そう、難しいですね。私も若い頃は可成り生活が乱れてましたから」
「ヨーダさんがですか?」
「はい、酷いもんでした」
この風貌なら若い頃は群がる女性の相手をして生活も乱れていたのかもしれないと思った。小河原は網の上の肉をトングで掴み依田の取り皿に乗せようとした。
「あ、お肉はちょっと……」
依田は皿の上に手を翳しこれ以上はいらないと断る仕草をした。
「お肉はお嫌いでしたか?すみません」恐縮して小河原は頭を下げた。
「いえ、違うんですよ。好きなんですがちょっと最近太って来たもので」
依田は少し照れたようにして白髪の頭を撫でていた。
「依田さんが体型を意識するなんて意外です」
「私は太ると直ぐ顔に出るんですよ」
小河原は彼のような年輩が未だに自分の体型を気にするとはさすがにダンディーな紳士だと感心していた。
少し離れた所で座る咲知がじっと小河原を見つめていた。小河原は咲知に微笑んでみせた。二人だけしか分からない微かな仕草をマンジョビッチが見逃さなかった。
「いいなあ、オガちゃんとマーちゃん。熱々でさあ~」
マンジョビッチが羨ましそうに膨れっ面で言った。
「そうそう、ねえ、二人はさあ、どう言う体位でするの?」
「どっちがタチでどっちがネコなの?」
オカマたちが咲知と小河原に卑猥な質問し始めた。どの質問にも咲知は「そんなんじゃないわ」「違うわよ」と旨い具合にはぐらかしていた。その咲知の受け答えが余裕に見えたのかマンジョビッチがさらに酔いに任せて絡んで来た。
「ふん、何さ。幸せでございますみたいな顔しちゃってさ。悔しー!」
「マンジョビッチだってそのうちいい人が現れるわよ」
ビン子ママが慰めた。
「私だって昔はいい男がいたわよ。お前のA(アヌスのこと)は素敵だよってこうやって舐めてくれるの」そう言ってマンジョビッチは目の前にあるまだ生のホルモンを箸に取り舌を出してちろちろと舐め始めた。
「バカ!ホルモンが食えなくなるだろ!」「マンジョビッチ、最低!」「下品!」
マンジョビッチに一斉に罵声が飛んだ。
「あー、男が欲しい」
マンジョビッチが切ない声で嘆きながら焼けたホルモンを口に入れた。
「あたしも」「あたしも~」欲求不満のオカマたちが発情した猫ように合唱した。
一人奥で座っていた美形の若いオカマが「皆さん、大変ね~」と一言。
「あんた、少しぐらい可愛いからって何よ。後十年、二十年経つとこうなるのよ」
マンジョビッチが罵った。
「そうよそうよ。あんたなんかきっと太るタイプね。早めにデブ専の相手を捜すことね」
他のオカマたちは今度はマンジョビッチに味方した。
「私はちゃんと彼氏がいます。残念でした~。オネエさんたちこそ永久に彼氏なんかできないんだからぶくぶくに太っちゃっても問題ないんじゃない?」
若いオカマが減らず口を叩く。可愛い顔をしているが他のオカマたちよりも性格が悪かった。いつも最後は年上のオカマたちに虐められていたが若いオカマも負けてはいなかった。
「あんたみたいなおバカ、すぐ捨てられるわよ」マンジョビッチが言う。「言ったわね~!あんたなんか筋肉お化けじゃないの」と若いオカマが応酬。賑やかな宴席だった。
オカマたちは膨大な肉を平らげ大量のビール、マッコリを飲み干し二時間程で戦場のような食事会は幕を閉じた。彼女たち(?)はこれから巣穴に戻りきっと泥のように眠るのだろう──。