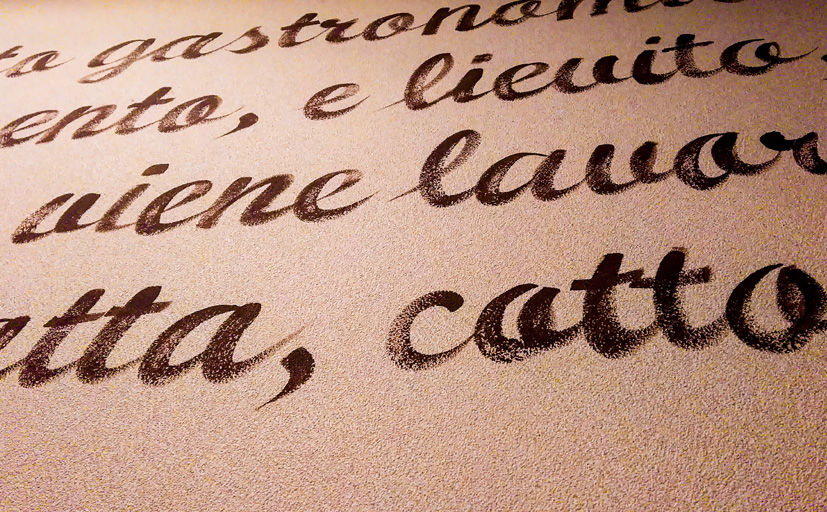月曜日、出社早々、営業部長から内線でデスクまで来るように指
「それを良く読んでもらえば分かると思うが、ざっと言うと競合プレゼンで十日後にアイデアを三案提出しなければいけない。他の部は結構忙しいから君の課にお願いする。企画内容はそこに書いてある通りで他に説明することは何もない。君の課の部下を使って上手くやってくれ。野村君と勝木君に協力してもらってもいいんじゃないか?」二人の名前を口にした時、部長は初めて小河原に視線を向けて続けた。
「素案ができたらプレゼン前にまず私に見せること。当日のプレゼンの日には私も同行する。勿論、野村君、勝木君も連れて行く。宜しく頼むよ。以上!」
あの二人と仕事をするのは気が重かったがこれを乗り切らなければ小河原に未来はないと思った。自分の席に戻り、野村と勝木を呼んだ。二人は敵愾心を露にして近付いて来た。
「なんすか?」野村がやる気なさそうに質問する。勝木はあらぬ方を見ている。
「二人にプレゼンを手伝って欲しいんです」コピーしたオリエンシートを二人に渡そうとすると「もうやりたくないって言ったでしょ!」と野村が急に声を荒げた。他の課の社員たちの視線を一斉に感じた。
「ちょっと待ってください。今回は営業部長が君たちを起用してくれと名指しで要望があったんです。部長は君たちに期待しています。引き受けてもらえませんか?」多少嘘も織り交ぜて、下手に出て説得した。野村も勝木も無言でオリエンシートを受け取った。
「そのシートに細かく書いてありますが、十日後のプレゼンですから明後日一度、アイデアをそれぞれ持ち寄りましょう。それまで皆さん、じっくり考えてください」
前回、野村の企画書を早めにチェックしなかった反省からまず三人で企画内容を詰めてこれから段階を追って二人の企画書をチェックしようと思った。それにしても勝木と野村、この二人と仕事をするのは気が重かった。
昼休みになって奥の扉から出て行く咲知を目で追いながら小河原も違う扉から慌てて廊下に出た。エレベーターホールに向かう咲知に追い付いた。
「咲知さん」
後ろから呼び止め彼女の腕を取って誰もいない会議室に連れ込んだ。会議室は暗く小河原は照明を点けずに入り口の直ぐ側で咲知に話し始めた。その時、小河原はドアが少し開いていたのを気付かずにいた。
「実はあの後、自宅に帰って妻から追い出されてしまいました。面目ない話です」
「それで今、どこに泊まってるの?」心配そうに咲知が小河原の顔を見つめている。
「会社の側のビジネスホテルです」
「何日泊まってるの」
「三日になります」
「本当にしょうがないわね。何で私に連絡しないの?」
咲知が口を尖らせて小河原に詰め寄る。
「いえ、ご迷惑になるかなと思って……」小河原は叱られた子供のように恐縮した。
「ご迷惑って……同棲してくださいって言ってる人が何を遠慮してるのよ?今晩からうちにいらっしゃい!」
咲知が小河原の腕を取って言う。
「咲知さんのマンションに行っていいんですか?」
「だって行く所ないんでしょ?」
終業時間にはまだ間があったが、会社近くの三日間滞在したビジネスホテルに戻り、荷造りをして咲知のマンションに向かった。午後からずっと小河原は興奮した自分の気持ちを抑え切れなかった。咲知が自ら同棲を望んだ訳ではなく、妻から追い出された小河原を不憫に思って同棲できるようになっただけだがそれでも小河原は自然と口元が緩んでいた。咲知のマンションに向かう途中、電車のドアのガラスに自分の間の抜けた顔が映っていた。口元をきっと結び自分を窘める。しかしまた知らずに笑みが零れてしまう。咲知のマンションのドアチャイムを鳴らすと一足先に帰宅した咲知の穏やかな顔が現れて、小河原は増々浮かれ相好を崩した。咲知はシルクの白いキャミソールとショートパンツの部屋着を着ていた。玄関の三和土で咲知が小河原の手を引いた。靴を脱いで框に上がると咲知は優しく抱きしめてくれた。耳元で囁いて言う。
「どうなるか分からないけど一緒に暮らしてみましょう」
「すみません」
「ばかね。何、謝ってんのよ」
トランクを引いて廊下を数歩前に進むと、部屋のどこも整然と片付いていつものように微かな薔薇の香りが漂っている。小河原は振り返り咲知を抱きしめキスをした。レモンイエローのソファーに二人は崩れ落ち、小河原は咲知が着ていたキャミソールをたくし上げ咲知の乳首をそっと口に含んだ。咲知は小さく身を捩って小さく喘いだ。小河原は久しぶりに自分の中に男の存在を感じた。咲知のショートパンツとその下の下着に手を掛けると彼女はそれを制して逆に小河原のズボンと下着を下ろし小河原の物を手に取った。ノーマルな異性同士の愛し方ではなかったが、小河原は肉体的に精神的に満たされて行った。咲知は上半身の肌を晒して小河原は下半身何も纏わず、暫く二人はちぐはぐな格好でソファーの上で抱き合っていた。この刹那、小河原は何とか一緒にやって行けるのではないかと言う自信にも似た気持ちが生まれた。
徐に咲知が髪を後ろに束ね、台所で何やら料理を始めた。スパゲティを茹でている。適当な大きさに千切ったレタスとカットしたトマトをサラダボウルに盛って市販のサラダドレッシングで和えていた。スパゲティが茹で上がるとまた出来合いのミートソースをフライパンで一緒に炒め十五分程で夕飯ができ上がった。何でもないようなスパゲティとサラダが咲知と一緒だと三ツ星の高級レストランのメニューのように思えた。
咲知と暮らし始めて小河原は仕事もプライベートも順調だった。部長に依頼されたプレゼンの準備も当初、野村と勝木は渋々作業していたが、何回か打ち合わせを重ねるうちに真剣に取り組むようになった。小河原と咲知は相変わらず社内では距離を置いていた。以前のように距離はあっても精神的な隔たりがある訳ではない。幾ら社内で咲知が冷たい態度を取ってもそれが演技だと分かっていたから辛くはなかった。ただこれ以上噂を広げないために、二人の関係を秘密にするために、朝はそれぞれ別々に出社、夕刻も別々に退社し咲知のマンションに帰宅した。まだ数日だが小河原は咲知の部屋にすっかり落ち着いてしまった。
今夜は咲知の二丁目の出勤日だった。小河原が退社しようとすると咲知はまだ残業していた。小河原の携帯にメールが入った。
〝今日はお店に出勤します。先に休んでいてください〟咲知からのメールだった。
小河原も咲知と暮らすようになって携帯メールの操作方法を覚えた。
〝明日は休みだから、あなたの帰りを待っています〟
小河原は返信してそのメールを読んで頷く咲知を遠目で眺めていた。
咲知の帰りを待って起きているつもりが疲れのせいかソファの上で簡単に寝入ってしまった。翌朝目覚めるとベッドの上で白い咲知の背中が横たわっているのが見えた。咲知は小河原に毛布を掛けてくれたようだ。生憎の鈍色の雲が広がる雨空だったが、却って気分は落ち着き充足感に満ちていた。咲知の部屋に掛かっていたシンプルな数字だけのカレンダーを見て多分もう梅雨入りなのだろうと思った。毎年、自宅で過ごしていた梅雨の時期は家中の雰囲気が一層重苦しく感じ、暗い書斎の隅で息を潜め、やがて自分が深い奈落の底に落ちて行くような錯覚を覚えていた。今では憑いていた全ての悪い物が払い除けられて自分の体が軽く感じる。
愛情を抱いた相手が男であっても、自分は今咲知を愛しているのだと実感している。その自分の気持ちにもう戸惑いも後悔もなかった。この世の誰よりも咲知を愛していると胸を張って世界中の人たちに自慢できるような気がした。
昨夜は帰りが遅かったのかまだ咲知は熟睡していた。ソファに掛かっていた洋服を着て、音を立てずに洗面所に向かい、化粧台の上にあった歯磨きのチューブから歯磨き粉を指の上に捻り出し丹念に磨いた。顔を洗ったがタオルが見当たらずタオル掛けにあったタオルで顔を拭いた。タオルの中に咲知の匂いがして顔を埋め思い切り咲知の匂いを嗅ぎ取ろうとした。
自宅から持って来た一冊の読み掛けの本をトランクから取り出して窓際の微かな光で読み始めた。自宅ではストレスのせいで読書にさえ集中できなかったが、この部屋では本の中の世界に浸れることができた。暫くすると溜息のような寝息が聞こえ咲知は寝返りを打つと小河原の方をじっと見つめていた。
「そんな暗い所で読んでると目に悪いよ」微睡んだ目で咲知が呟く。
「いや、暗がりで読むのは慣れていますから……」
「余り私に気を遣わないでね。それから敬語を使うのももう止めて」
咲知の口調が少し寂しげに聞こえた。
「うん、分かった」と小河原はくだけた口調で返事をした。
「ねえ、今日は外で食事をしましょう。それからあなたの身の廻りの物も揃えなくちゃね」そう言いながら咲知は上半身を起こして部屋着を羽織りベッドから下りた。洗面所から戻ると咲知は清々しい顔つきで着替え始めた。髪を後ろに束ねながら「さ、行くわよ」とタンクトップと薄手のローライズのジーンズに身を纏い、小河原は眩しげにその姿を見た。マンションを出て静かな裏通りから地蔵通りに出ると活況な商店街に出くわす。暗い雨空にも関わらず人出が多く、世の不景気はどこ吹く風と言った感がある。咲知と地蔵通りをそのまま西巣鴨方面に五、六分程歩くと小さなイタリアレストランが見えた。店の前には小さな黒板にランチコースのメニューが書かれていた。店内は狭かったが家庭的な造りで居心地は良さそうだった。咲知と小河原は席に付くと三種のパスタから一つを選んで前菜とスープとデザートの付いたコースを注文した。
「ワインでも頼みましょ」咲知は小河原の返事を待たずにウェイターにグラスワインの赤を注文している。咲知のてきぱきとした決断が気弱な小河原には頼もしくまた気楽であった。咲知は鼻歌を歌いながら外の景色を漫然と眺めている。その横顔を小河原は慈しみを持って眺めている。グラスワインが二つテーブルの上に置かれ二人はグラスを合わせた。「あなたのご家族は大丈夫なの?」咲知が改まって言う。「大丈夫。妻も息子も私がいなくてせいせいしてるよ」咲知はグラスをテーブルにおいて座り直して言った。
「でも前に言ったように奥さんと息子さんの面倒はきちんと見てあげなくちゃだめよ」
「はい、大丈夫です」咲知が安心するように真剣な素振りで大きく頷いた。
「今でもあなたと一緒に住んでいいのか迷っているんだもの……」
咲知は眉を寄せてワインに口を付けた。
「余り気にしないでください」
「気にするに決まってるじゃない。私はあなたの家庭を壊しているのよ」
「いえ、咲知さんのせいで壊れている訳じゃないよ。それに咲知さんがいてもいなくてもいずれ私はあの家から出て行った筈です」
「そう……でももしあなたが帰りたくなったらいつでもおうちに帰るのよ」
軽く相槌を打ったがそれはあり得ないだろうと小河原は心の中で思った。ウェイターが次にサラダをテーブルに置いた。咲知とは二度目の外食で気持ちは子供のように浮かれていた。小河原はアンチョビとベーコンのペペロンチーノと過去一度も食したことのないスパゲティを注文した。咲知はトマトソースのスパゲティを頼んでいた。小河原はペペロンチーノは案外辛いのだなと思った。咲知は小河原の気持ちを察したのか「こっち、食べて見る?」と優しく勧める。「うん」そう言ってスパゲティの皿を交換した。トマトソースのスパゲティもちょっと食べ慣れない味だった。喫茶店のケチャップ味のスパゲティが好きな小河原にはこのスパゲティが上品で高級に思えた。スパゲティも、サラダも、スープも、デザートも、この店も、厚い雲で覆われているこの天気も今は好きになれそうだった。何より目の前に咲知がいることに満足していた。こんなランチもあるのだ、こんな生活を毎日送っている人間もいるのだと思うと自分の今までの人生が無駄に思え後悔の念にかられた。
「咲知さん、一つ聞いていい?」
「何?」
「咲知さんは私のことどう思ってるんですか?」勇気を出して聞いてみた。
「そうね。私を愛してくれているのが分かるから嬉しいわ」
「いえ、そうじゃなくて私のことを好きなのか聞きたいんです」
「そんなこと聞きたいの?」咲知が呆れた顔をして言う。
「はい」少しの間があって小河原は焦れた。
「ヒ・ミ・ツ」はぐらかされた。
ランチが終わり店を出ると咲知が私の腕に手を絡ませて来た。前のように気恥ずかしい気持ちも沸き起こらなかった。ただふわっとした胸のときめきを感じた。この歳で若かりし頃のあの青臭い感情を思い起こせるとは思わなかった。
小河原は洋装店で部屋着、パジャマを、食器店で茶碗、箸、マグカップを日用品店では歯ブラシと髭剃りを買った。咲知もパジャマとマグカップは色違いのお揃いを選んで買った。今夜から互いに水色と薄紅色のパジャマで寝て、翌朝は黒と白の有田焼のマグカップでコーヒーを飲むのだろう。妻の由起とは経験したこともない、まるで新婚生活を迎えるような気恥ずかしくも甘いムードを味わっていた。通りの雑踏の中を買い物で二時間も歩いたが、不思議と疲れは感じていなかった。